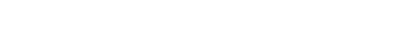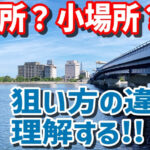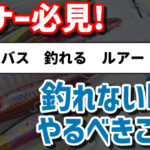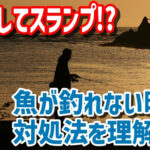最近のルアーフィッシングシーンでは、多関節のクネクネ動くルアーや、本物のベイトフィッシュのカラーを追求したリアル系カラーが話題を呼んでいます。
確かに、リアル系ルアーはアングラーの購買意欲をかき立てます。
しかし、実際には、本物とは似ても似つかないド派手なチャート系カラーでシーバスが釣れることも非常に多いです。
あるいは、昔から定番中の定番カラーといえばレッドヘッドです。
なぜ、リアル系ルアーが勢力を拡大しているのに、本物に似ていないルアーでも釣れるのか?
それは、「ルアーはエサではない」からに他なりません。
このページでは、エサではない、ルアーでシーバスを狙うことの面白さをご紹介します。
先人が遺した言葉
本物に似ていることは重要ではない
.jpg)
僕がルアーフィッシングを始めた頃に、雑誌やテレビでけっこう見聞きしていた先人の言葉があります。
その先人の言葉が『ベイトフィッシング(エサ釣り)』と『ルアーフィッシング』の違いを端的に表現しているといわれています。
(中略)
たしかに、小魚やカエルそっくりなルアーにすれば、フィッシュイーターの性格や習性をなにも分かっていない”アングラーは釣れる”かもしれない。
でも、「本物そっくりにする」ということは、フィッシュイーターのバイトを誘発する要素にならないというのは間違いない。
translated by Showcalla
これは、世界で初めて『プラグ』タイプのルアーを世に送り出したジェームズへドンの言葉として語り継がれています。
 ショーカラ
ショーカラちょっと今風に脚色して訳しましたが、原文はこんな感じ↓です。
高校生程度の常識があれば普通に読めるような平易な言葉で書かれているので、興味があれば原文を読んでみてください。
そして、訳文と対比させた部分がコチラ↓。
“ストライク“ってのがなんのかわかりませんが、だぶん「魚が口を使うこと(バイト)」でしょう。
 ショーカラ
ショーカラルアーに組み込まれた『機能』がストライクを引き出す
ジェームズへドンはプラグを作る過程で、当然、プラグを本物に似せるということをしたそうです。
でも、本物の小魚やカエルに似せても似せても似せても似せても…
納得のいく結果は得られませんでした。
ジェームズへドンによれば、プラグを本物そっくりに作り上げていっても得られるものは何ひとつなかったそうです。
そこで行き着いた一つの結論が
ということです。
 ショーカラ
ショーカラへドン流に”ストライク”を考察してみる
たとえば、本物のベイトにそっくりなルアーで魚が釣れたとします。
この魚が釣れた理由をへドン流に解釈すれば
 J・へドン
J・へドンそのルアーが持つ「道具としての機能」によって魚のバイトが誘発されたんだ。
ということです。
へドンは、小魚やカエルそっくりなプラグ作りに着手しながら、結局、世界で初めて世に送り出したプラグは、小魚やカエルからはほど遠い形をしたルアーでした。
ジェームズヘドンの作った世界初のプラグ「Dowagiac Expert(ドウォージャック エクスパート)」は、現在では”スロープノーズ“という愛称で呼ばれています。
これが、今から120年くらい前のへドンが初めて世にプラグを送り出したときの話です。
エサじゃない!樹脂の塊で”ストライク”を引き出す!

第4回の記事でも少し書きましたが、
なぜ、シーバスがエサでもない樹脂の塊のルアーにバイトをするのか?
不思議に思ったことはありませんか?
⇒【ゼロから始める】シーバスを釣るために重要な5つのファクター【第4回】
ルアーは本物の魚の動きを再現できない
魚を詳しく観察したことない人であれば
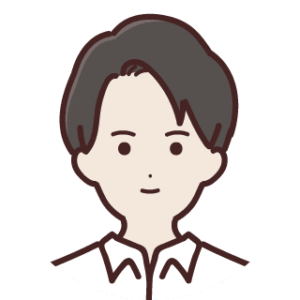 Aさん
Aさんという答えになるのかもしれません。
でも、本物の魚が泳いでいる様子と、ルアーが泳いでいる様子をじっくり観察してみるとすぐにわかります。
 ショーカラ
ショーカラまぁ、全然とまではいわなくても、それほど似ているわけではありません。
たしかに、ルアーも「泳いで」います。
でも、似ていない。
魚には背骨があって、その分だけ可動域があります。
しかし、ルアーはフロントからリアまで関節がありません。
また、ルアーの動きというのは、ローリング・ヨーイング(ウォブリング)・ピッチングという三種類のアクションの単調な繰り返しです。
どう頑張ったところで、本物の魚が泳ぐ姿に似るはずがありません。
シーバスはそれほど単純ではない
 Bさん
Bさんという考え方もあるかもしれません。
でも、僕はそうは思いません。
釣りの世界では「魚がスレていて、反応するけど喰わない」と言われる状況があります。
実際にスレているのかどうかは魚に聞いてみないとわかりません。
でも、少なくとも、
ルアーの動きに興味を示しつつも違和感を覚えて口を使うには至らない
ということは普通にあるという感覚です。
シーバスはとても賢い魚だ、とまではいいません。
しかし、「それほど単純でもない」というのが(おそらく)アングラーのコンセンサスじゃないでしょうか。
「道具としての機能」がシーバスの興味を惹きつける!
じゃあ、なぜプラスチックの塊にシーバスが喰いついてくるのか?
それは、ルアーそのものに
シーバスのバイトを引き出す「道具としての機能」が組み込まれている
といわれます。
魚っぽく泳いでいる樹脂の塊をエサと見間違えているわけではありません。
 ショーカラ
ショーカラというのが、エサではなく「ルアーでシーバスを釣る」というシーバスフィッシングの考え方です。
ルアーフィッシングをしない人たちは、ルアーのことを『疑似餌』と表現するのが一般的です。
でも、ルアーアングラーにとって、ルアーは疑似餌ではありません。
ルアーは『タックル(道具)』そのものです。
ロッド・リール・ラインと一緒で、ルアーも道具です。
これらのタックルを駆使してシーバスにアプローチをするのが、『スズキ釣り』ではない『シーバスフィッシング』です。
そのために、アングラーはルアーを動かし、場合によってはルアーの動きを止め、あるいはそれらを組み合わせるなど、ルアーと呼ばれる道具に備わっている機能を駆使していかなければなりません。
ルアーを動かすうえで重要な2つのファクター

樹脂(鉛)の塊であるルアーを動かしてシーバスのバイトを引き出すための重要な要素が二つあります。
◆ルアーのアクション
一つはルアーを動かすスピードです。リールを巻くスピードということもできます。
もう一つはルアーのアクションです。つまり、ルアーの動かし方そのものです。
ルアーのスピード

プラスチックの塊を使ってシーバスのバイトを引き出すために特に重要なのがルアーを動かすスピードです。
シーバスアングラーの中には、ルアーを動かすスピードをあまり重要視していない人もいます。
実際に、シーバスフィッシングに慣れてくればルアーを動かすスピードをそれほど気にしなくてもシーバスが釣れるようになってきます。
しかし、ビギナーの頃には、ルアーを動かすスピードというのはとても大切なファクターということを頭の片隅に置いて釣りをしましょう。
ルアーを動かすスピードが大切な理由
この『ルアー』と呼ばれるプラスチックの塊には、シーバスのバイトを引き出すための多くの機能が組み込まれています。
色・見た目・動きの種類や幅・動きのスピードなど。
これらルアーに組み込まれた多くの機能が複合的に作用して、本物の小魚とは似ても似つかない樹脂の塊に対するシーバスのバイトを引き出します。
そのルアーに組み込まれた機能のうち、ルアー1個だけで最も多くの変化点を生み出せるのがルアーを動かすスピードです。
ルアーのカラーやシルエットといったビジュアル面に変化をつけようとすると、ルアーそのものをチェンジする必要があります。
たとえば、シルバー系のカラーからゴールド系のカラーにチェンジしたり。
あるいは、140mmクラスのルアーから70mmクラスのルアーにチェンジしたり。
さらには、細身のシンキングペンシルから体高のあるシンキングペンシルにチェンジしたり…。
でも、スピードは違います。
ルアーを動かすスピードというのは、ルアー1個でさまざまな変化点を作り出すことができます。
1秒間にリールのハンドル半回転というような超デッドスローから、1秒間にハンドル1.5~2.5回転くらいのファーストリトリーブまで。
ルアーの動きが破綻しない範囲でさまざまなスピードの変化を作ることができます。
あるいは、ルアーを巻いてる途中でもスピードの変化をつくることができます。
最初は超デッドスロー→途中で一瞬だけ早いスピード→止める
といった感じで。
シーバスの興味をプラスチックの塊に惹きつけるためにさまざまな組み合わせができるのがルアーを動かすスピードなのです。
中級者以上のアングラーにルアーを動かすスピードが軽視される理由
「ルアーを動かすスピードを変化点としてシーバスのバイトを引き出す」ということを口うるさく語るプロアングラーってほとんどいません。
あるいは、プロアングラーでなくても、たとえば自分にシーバスフィッシングのいろはを教えてくれた師匠のような存在の人であっても、ルアーを動かすスピードにこだわれって教える人はすごく少ないと考えられます。
これはなぜか?
実は、プロアングラーが基本にしているルアーのスピードと、一般アングラーが基本にしているルアーのスピードは、実際のところそんなに差がないといわれています。
これは、どんなスピードでルアーを動かしても釣れる、という意味ではありません。
たとえば、1秒間にハンドル1.2回転くらいのスピードでリールを巻くプロアングラーがいたとします。
じゃあ、一般アングラーはどのくらいのスピードで巻いてるか?といえば、プロアングラーと同じリールを使っている一般アングラーも、1秒間にだいたい1回転~1.3回転くらいのスピードで巻く、という感じみたいです。
それぞれのアングラーがベースにしているリールを巻くスピードって、実際にはそれほど幅はないのです。
ベテランアングラーになればなるほど「このくらいのスピードで巻くのが一番釣れる!」というスピードを経験的・体感的に知っています。
なので、だいたいのアングラーのスピードが近似してきます。
そのため、少しシーバスフィッシングに慣れてきた人であれば「だいたいこれくらいのスピード」っていうベースがあって、基本的には「そのスピードで動かせば正解」という場合がかなり多いです。
そのため、ルアーを動かかすスピードについて師匠や上級者から語られる機会が少なくなってしまいます。
それでもルアーを動かすスピードが重要な理由
ビギナーにはルアーを動かすスピードのベースがない
それでも、僕がルアー動かすスピードにこだわる理由は2つ。
一つは、ビギナーの頃は経験値が不足しているため、ベースにできるようなルアーのスピードがあるわけではありません。
なので、ルアーを動かすスピードにこだわるように紹介しないと、ルアーを動かすスピードが軽視されてしまいます。
 ショーカラ
ショーカラちなみに、どれくらいのスピードでルアーを動かせばいいのか?といえば、目安は、
1秒間にリールのハンドル1回転
です。
もちろんリールのギア比によってルアーの動くスピードは変わってきます。
ただ、それくらいを目安にしておけば大きく外れることはありません。
 ショーカラ
ショーカラアプローチ方法の選択肢を増やす
ルアー動かすスピードにこだわるもう一つの理由は、ベースのスピードで魚が反応しないときにどうすればいいのか?という問題について
ルアーを動かすスピードを変えることでシーバスを惹きつける
という別のアプローチ方法を選択肢として持っておくためです。
おおむね6~7割くらいのケースにおいて、ベースとなるルアーのスピードを貫いてもらえれば問題ありません。
問題は「そのスピードではシーバスのバイトを得られない場合に何をすればいいか?」ということです。
 ビギナー
ビギナーといってあきらめるのもの選択肢の一つです。
あるいは
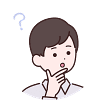 ビギナー
ビギナーといってルアーチェンジをすることも選択肢の一つです。
でも、その他の選択肢として、
 ビギナー
ビギナーという考えも持っておいた方が圧倒的に釣りの幅が広がります。
ルアーを動かすスピードに変化をつけるというのは、なにも、変化させたスピードによってバイトを引き出すことだけが目的ではありません。
ルアーを動かすスピードに変化をつけることで、今までシーバスから異物として見られていた樹脂の塊に興味を惹きつけることもできます。(食いつくかどうかは別にして)
今まで興味を示さなかった樹脂の塊に対して、シーバスの興味を惹きつけることもルアーのスピードに変化をつけることの役割といえます。
ルアーのアクション
樹脂の塊であるルアーに対してシーバスのバイトを引き出すためのファクターのうち、ルアーのスピードと並んで重要なのがルアーのアクションです。
これも、シーバスフィッシングの中級者くらいになってくるとあまり重要視されない要素です。
ルアーのアクションが重要視されない理由
シーバスフィッシングの中級者以上のアングラーにルアーのアクションが重要視されない理由としては、タダ巻きでも十分にシーバスが釣れてしまうということが挙げられます。
新製品ルアーを紹介するプロアングラーですら
 某プロ
某プロトゥイッチみたいなアクションはさせずに、ただ巻くだけ。
という説明をします。
 ショーカラ
ショーカラ某プロが言いたいのは
 某プロ
某プロということでしょうが、ビギナーの中には
 ビギナー
ビギナーと誤解する人が必ずいます。
なので、中級者くらいのアングラーからはルアーのアクションが重要視されない傾向にあります。
 ショーカラ
ショーカラタダ巻きで釣れる理由
では、なぜ、本物のベイトに似ていない樹脂の塊のタダ巻きでシーバスが釣れるのか?
はっきり言って、ルアーのタダ巻きって本物の魚の泳ぎと比べると全然似てないんですよね。
僕がいままで見た中で一番本物の魚に似ていると思ったのはハドルストンのハドルトラウト。
これは、ほかのプラグやビッグベイトから比べると、(人間の目からは)圧倒的に本物っぽく見える。
まぁ、ほかにも本物に似てるルアーはあると思いますが、それは今はどうでもよくて…
ほとんどのルアーは、泳いでいても本物の魚っぽい泳ぎではありません。
それなのに、なぜタダ巻きで釣れるのか?
それは、ルアーには、ルアーが動くことによってフィッシュイーターのバイトを引き出す機能が組み込まれているからだと説明されるのが一般的です。
これは「そのルアーに本来的に組み込まれた機能」という意味でビルト イン アクション(Built in action)と呼ばれたりします。
タダ巻きで釣れないときはどうする!?
問題は、「基本となるアクション(タダ巻きによるビルトインアクション)で釣れないときにどうすればいいのか?」ということ。
一つは、ルアーを動かすスピードの場合と同様に、ルアーチェンジする方法があります。
違うルアーのビルトインアクションに頼ってシーバスのバイトを引き出すためのアプローチを試みる。
これも選択肢の一つです。
でも、もう一つ考えられるのが、同じルアーの別のビルトインアクションでアプローチを試みる方法です。
当然のことながら、ルアーには、タダ巻きから生まれるビルトインアクション以外にも多くのアクションが組み込まれています。
トゥイッチ・ジャーク・リッピングによるアクション。
ジャークの中でも短くて強いジャークや長めの弱いジャーク。
タダ巻きの途中で織り交ぜるトゥイッチ。
…など色んなパターンが考えられます。
タダ巻きのビルトインアクションに口を使わなかったシーバスが、これらタダ巻き以外のアクションに変えることでプラスチックの塊にバイトしてくれることがあります。
また、ルアーのアクションは、シーバスのバイトを引き出すことだけが目的ではありません。
ルアーのアクションに変化をつけることで、今までシーバスから異物として見られていた樹脂の塊に興味を惹きつけることもできます。
今まで興味を示さなかった樹脂の塊に対して、シーバスの興味を惹きつけることもルアーのアクションを変えることの役割といえます。
日本と海外のルアーフィッシングに対する考え方の違い

最後に、日本におけるルアーフィッシングと海外におけるルアーフィッシングの考え方の違いについて少しだけご紹介しておきます。
数年前にウェブメディアで「日本のルアーフィッシング」について、釣り好き外国人が興味深い記事を書いていました。
その記事によれば
しかも、少しずつ、ベイトフィッシングに近づいている。
という趣旨の内容でした。
記事を書いたのは、日本で生活していて、日本で釣りを楽しんでいる釣り大好きなヨーロッパ出身のおやじだそうです。
これは日本のルアーフィッシングに対するそのおやじの一評価にすぎません。
ただ、この記事を読んだとき、遠い昔、僕がルアーフィッシングにハマり始めた頃に当たり前のように語られていた「ルアーで魚を釣る」という釣り方について再認識するきっかけになりました。
ヨーロッパ出身の釣り好きおやじの記事を読んだ当時は
 ショーカラ
ショーカラって程度の感想しかありませんでした。
でも、近年になって猛烈に市場に出回り始めたのがいわゆるリアル系カラー。
狂鱗とか強鱗とかライブベイトカラーとかアデルとか…。
当時の釣り好きおやじが今の日本のようなルアーフィッシングシーンを予見していたわけではないでしょう。
ただ、その釣り好きヨーロッパ人のおやじからすれば
そんなにエサに似てた方がいいなら、もうエサでいいじゃん
って感じだったんだと思います。
 ショーカラ
ショーカラエサではない!プラスチックの塊でバイトを引き出す面白さ!!

見た目が本物っぽくない樹脂の塊でどうやってシーバスに口を使わせるか?
それは、シーバスフィッシングの面白さの原点といえます。
へドンの言葉を鵜呑みにする必要はありません。
しかし、へドンの言葉には、ビギナーが頭の片隅には一応置いておいた方がいい重要な内容も含まれています。
◆魚のバイトを引き出すために、ルアーのリアルさではなく、ルアーに組み込まれた機能を駆使する
ということ。
ルアーの見た目というのは、ベイトそっくりであってもなくても、別にどちらでも構いません。
 ショーカラ
ショーカラへドンが言いたいのは、ルアーフィッシングというのは
 J・へドン
J・へドン食べてみて~。
という受け身の釣りではないということだと思います。
「ルアーという道具に組み込まれた機能を駆使して魚のバイトを引き出すことがルアーフィッシングである」ということを100年以上前に語っていたのです。
シーバスを狙ううえで、古典的なルアーフィッシングスタイルか?餌釣り寄りのルアーフィッシングスタイルか?を決める必要はありません。
ただ、日本のようなエサ釣り寄りのルアーフィッシングスタイルの場合でも、「手持ちのルアーで釣れないときにどうアプローチするか?」ということを常に考えておくことはとても有効です。
「ルアーに組み込まれた機能を駆使して魚のバイトを引き出す」というスタイルは、選択肢として持っておいた方が釣りの幅が広がります。
ビギナーがシーバスフィッシングを始めると、どうしても「ベイトが〇〇のときは、あのルアーが…」と考えがちです。
エサ釣りで「今日は濁りがあるから、餌は匂いのキツイこの刺し餌」という発想に似ています。
でも、ルアーフィッシングというスタイルの中には、日本風の待ちのスタイルだけではなく、ルアーの機能を駆使して魚のバイトを引き出すというスタイルもあります。
手元にいろんなルアーを揃えることもシーバスにアプローチをするためにとても有効です。
しかし、1つのルアーでも道具として様々な機能が組み込まれており、それを駆使してアプローチするというアプローチ方法があるということは、意識として常に持っておくといいでしょう。