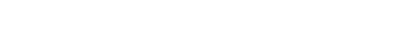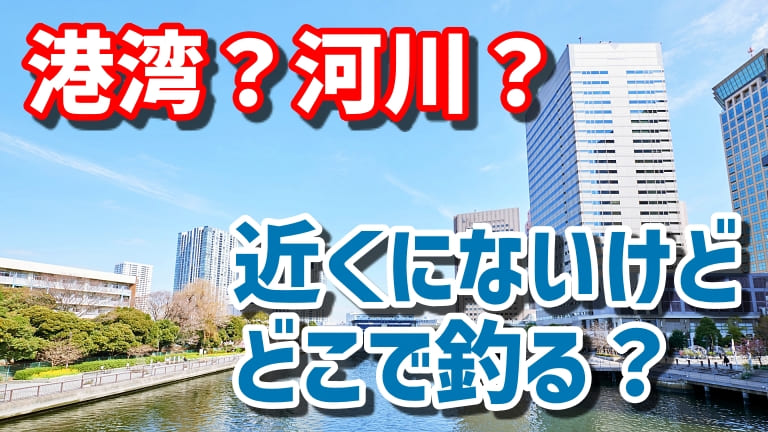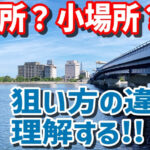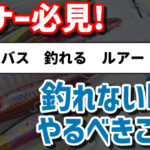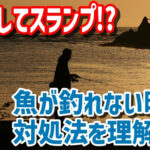シーバスは北海道と沖縄をのぞく全国各地の沿岸部で狙うことができる身近なターゲットです。
でも、シーバスを始めたばかりのアングラーは経験値が絶対的に少ないので「どんな場所でシーバスを狙えるか?」ということはわかりません。
あるいは、シーバスフィッシングでよく耳にする「河川」とか「干潟」とか「港湾」っていわれても、自分の家の近くにそれらのフィールドに当てはまる場所がないってこともありえます。
このページでは、シーバスフィッシングの主なフィールドと、フィールドカテゴライズの役割についてご紹介します。
シーバスフィッシングのフィールド
港湾部

いわゆる「港」「ベイエリア」です。「漁港」もそのうちの一つです。
港湾部はシーバスフィッシングの代表的なフィールドの一つです。
シーバスが餌となるベイトを捕食するのに身を潜める場所がたくさんあるのでシーバスの出入りの多いエリアです。
港湾部は常夜灯が多いので、シーバスの餌となる小魚が集まりやすいのも特徴です。
また、港湾部は足場がいいのでとても釣りをしやすい場所で、初心者におすすめのフィールドといえます。
ただし、港湾部はアングラー以外の住民や港湾関係者の利用も多いため、釣りをするときは周辺に十分に注意して下さい。
都市型河川


港湾部と並んでシーバスフィッシングを代表するフィールドが都市部を流れる河川や水路です。
常夜灯や街の明かりでベイトとなる小魚が集まりやすく、シーバスが身を潜める場所もたくさんあるので、シーバスの数も多く、シーバスフィッシングでは人気のあるフィールドです。
都市型河川もアングラー以外の住民の利用が多いので、釣りをする際には歩行者等に十分に注意して下さい。
大・中規模河川


河川は大型シーバスが釣れるポイントとして高い人気を誇ります。
九州や北陸の河川では毎年メーターオーバーのシーバスが何本も釣れています。
狩野川(写真1)や雄物川(写真2)はリバーシーバスの聖地ともいえる河川です。
ただし、河川の中にはウェーダー(胴付長靴)を履いて水に浸かって釣りをするというスタイルのフィールドがたくさんあります。 (これをウェーディングといいます)
また、河川の水位と水量は雨の影響を非常に受けやすいので身の安全を守るための細心の注意が必要です。
河川は中・上級者向けのポイントといえます。
なお、国道交通省のウェブサイトから河川の水位情報を確認することができるので、ぜひ活用しましょう。
⇒国道交通省「川の防災情報」
サーフ

いわゆる「〇〇浜」とか「〇〇灘」という名前のついているフィールドです。
僕の住む地域にも「弓ヶ浜」というサーフがあります。
サーフは足場が良く、また、青物やヒラメ・マゴチといったゲストに遭遇することも少なくないので人気のポイントです。
大型のシーバスもけっこう回遊してきます。
地磯

主に外洋に面した海岸線が地磯です。
磯の種類には、船で渡る沖磯と、歩いて行ける地磯があります。
シーバスフィッシングのメインのフィールドは地磯の方です。
もちろん沖磯でもシーバスを狙うことができますが、シーバスを狙うために渡船で沖磯まで渡る人はそれほど多くはありません。
(お手軽に釣れるのがシーバスフィッシングの魅力なので…)
地磯は外洋に面しているため青物や根魚との遭遇率も高いです。
また地磯には、一般的なシーバス(スズキ)のほかに「ヒラスズキ」という別の種類のシーバスが生息しています。
ヒラスズキ専門で狙うアングラーもたくさんいます。
地磯は大型シーバスやヒラスズキ、青物が狙えるので人気の高いフィールドです。
ただし、地磯は足場が悪いうえに波も被るので、シーバスフィッシングのフィールドとしては上級者向きといえます。
干潟

「干潟」とは潮の干満差によって干出と水没を繰り返す砂泥質の平地のことです。
干潟には潮の満ち引きによって「スリット」と呼ばれる水の通り道ができます。
ここは、水だけでなくシーバスの通り道にもなります。
干潮時には海底が露出して釣りにならない場所もあるので、潮汐表を見ながら潮の干満に合わせて釣りをすることになります。
干潟の釣りはウェーディングスタイルが基本になるので少し敷居が高いですが、あたり一面が海なので360°どこでもシーバスが狙えます。
自分の立っている場所の背中側でシーバスがベイトを捕食することさえあります。
防波堤

防波堤は足場がいいのでファミリーフィッシングに人気のポイントです。
ただし、足場が高いのでシーバスを狙うときにはほとんどの場所でタモ(玉網)が必須になります。
また、足場が高いので万が一に落水した場合には容易に上がることはできません。
必ずライフジャケットかフローティングベストを着用しましょう。
防波堤には消波ブロックが置いてあるところが多く、消波ブロックの上から釣りをしている人もたくさんいます。
釣りが禁止されていない限り消波ブロックの上で釣りをすることは可能ですが、消波ブロックの上は足場が不安定で危険なので、安全確保は十分に行ってください。
家の近くにシーバスフィールドがない!?
お住いの地域によっては↑に当てはまるようなフィールドが全然ないっていうところもあり得ます。
僕の地元である中海~宍道湖もその1つ。中海や宍道湖は先に挙げたフィールドに当てはまらない場所がほとんどなので
 アングラー
アングラー港湾? 河川?
って聞かれても
 ショーカラ
ショーカラって答えたくなるくらい↑の特徴に当てはまりません。
じゃあ、そんなときはシーバスが狙えないのか?とえいば、全然そんなことはありません。
むしろ、中海なんてほぼ全域でシーバスを狙うことができます。
問題は、↑に当てはまるようなフィールドが家の近くにない場合、どこでシーバスが狙えるのか?ってこと。
フィールドカテゴライズの役割は?
先に挙げたような「港湾」「都市型河川」「干潟」といったフィールドはシーバスが狙える場所を便宜的にカテゴライズしたものにすぎません。
便宜的とは具体的にどういう役割か?
1つはアングラーにとっての目安としての役割です。
「シーバスは日本全国の沿岸部であればどこでも狙えます!」って言われても、
 ビギナー
ビギナーって考えたとき、右も左も分からない入門者は暗中模索せざるを得なくなります。
それよりも、シーバスの集まりやすい場所をカテゴライズすることで、アングラーに対してシーバスが狙える場所の一応の目安を示すことができます。
もう1つは、釣り場はカテゴライズされていた方がメーカーなど業界にとって都合がいいからです。
たとえば、ほとんど長さの変わらないロッドでも、1本には「干潟マスター」ってサブネームが付いていて、もう1本には「港湾スペシャル」みたいなサブネームが付いていると、干潟でも港湾でも釣りをする人は両方買いたくなるでしょ。
どちらか1本の竿があれば全然対応できるのに、竿のテイストをわずかに変えて専門設計を謳うと売れるんです、この業界は。
欲しくなるんですよ、アングラーは。
「この釣りにはこのタックル、あの釣りにはあのタックル…」って感じで。
 ショーカラ
ショーカラカテゴライズはシーバスが釣れるフィールドを限定するものではない
これからシーバスフィッシングを始めるにあたって最も気をつけておかなければならないのは、「港湾」や「干潟」や「河川」といったフィールドのカテゴライズはシーバスが釣れる場所を限定しているわけではないということ。
つまり、そこに当てはまらないようなフィールドでもシーバスを全然狙うことができるということです。
 アングラー
アングラーと絶望する必要はありません。
海があればどこでもシーバスが釣れる可能性はあります。
しかも、きちんとポイントを見極めればその可能性は決して低くありません。
釣果情報は釣具屋で仕入れる(入門者の基本)
入門者にとってはポイント選びというのはとても難しいものです。
経験値が低いので「どういう場所で釣れるか?」というイメージがとても湧きにくいです。
そんなときは迷わず釣具屋で情報収集をしましょう。
お住いの地域でもっともHOTな情報を持っているのは地元の釣具屋です。
ウェブで当たり前のように釣り具が買える昨今、釣具屋が釣り客を呼び込むもっとも効果的な方法の一つは釣果情報で釣り客を釣ることです。
僕もそうですが、新しい釣果情報をたくさん持っている釣具屋に足を運びます。
とりあえずポイント選びに困った場合には釣具屋さんで情報収集しましょう。
 ショーカラ
ショーカラフィールドカテゴライズの役割を理解する!

◆フィールドの類型化は
①アングラーに目安を示す
②メーカーに都合がいい
ということでカテゴライズされている
◆「港湾」や「河川」等に当てはまらない釣り場でも普通に釣れる
シーバスが狙えるフィールドを「港湾」や「干潟」や「サーフ」というふうにカテゴライズすることは、入門者にとっては一応の目安になります。
ただ、これらに該当するようなフィールドが近くにない場合、
 アングラー
アングラーと絶望してしまうことにもなりかねません。
でも、このようなフィールドカテゴライズは、シーバスが狙えるフィールドを「港湾」や「干潟」や「河川」に限定するためのものではありません。
あくまで、アングラーのため、メーカーのために便宜的に類型化されたものにすぎません。
家の近くに「港湾」や「干潟」などに当てはまるようなフィールドがない地域でもシーバスは全然狙うことができます。
カテゴリーに当てはまるようなフィールドがお住いの地域にないときでも、釣具屋等で情報収集しながら積極的にシーバスを狙ってみましょう。
関連記事はコチラ↓