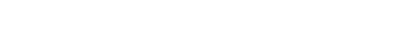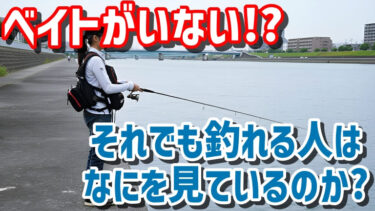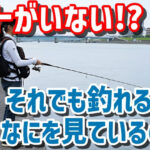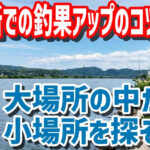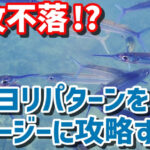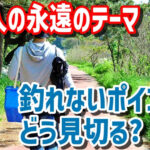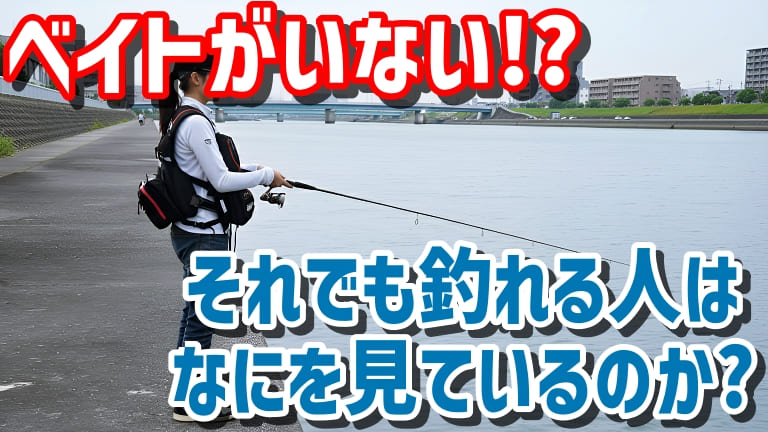
あれほど騒がしかったベイトの群れが、いつの間にか姿を消している。
表層に波紋もない。
そんな「ベイトに頼れない」状況に遭遇したことはないでしょうか?
 ビギナー
ビギナーと思いながらも、いつもと同じようにシーバスを狙う。
そして…反応なし。
しかし、他方で、それでも確実にシーバスを手にしている人もいます。
ベイトが抜けたあとでも釣果をあげる人と、そうでない人の違いはなんでしょうか?
このページでは、ベイトに頼らないシーバスの狙い方についてご紹介します。
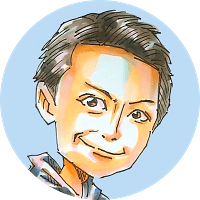
最近の釣りメディアでは、釣りに関する情報がメーカーのために中・上級者目線で発信されるようになりました。ナチュラルリリースでは、ビギナー目線で語られることが少なくなった「釣りに関する『キホンのキ』」をビギナー目線で発信しています。
FAQ(よくある疑問)

デイゲームでは「地形や流れの変化」といったベイトが溜まる可能性のある場所を狙います。
一方、ナイトゲームでは「明暗部」のようなシーバスが待ち伏せて捕食しやすい場所を狙いましょう。
デイゲームではベイトの溜まりやすい場所がシンプルに狙いやすいですが、ナイトゲームではデイゲーム以上に“シーバスが待ち伏せしやすい場所”がはっきりします。時間帯によってベイトやシーバスの行動は変わるので、その変化に合わせることが第一歩です。
ベイトが減ってもシーバスは消えない

ベイトが見えない日は、海の中まで静まり返ったように感じます。
でも、実際には、ベイトやシーバスがいなくなったわけではありません。
ベイトが散ったあとも、単発のシーバスや小規模の群れはまだ目の前に残っています。
この事実を信じてシーバスを狙い続けることができるかどうかが釣果の分かれ目です。
そして、ベイトが少なくなると、シーバスの行動は大きく2タイプに分かれます。
ひとつは、残ったベイトの小さな群れをしつこく追う(積極捕食タイプ)。
もうひとつは、明暗や障害物を利用して待ち伏せする(待ち伏せ捕食タイプ)。
つまり「ベイトが減る=シーバスがいなくなる」というわけではありません。
シーバスは、少なくなったベイトを効率的に捕食するため、ベイトが溜まりやすい場所やベイトを捕食しやすい場所に、よりシビアに居着くようになるのです。
そのためにシーバスは、流れのヨレや橋脚のわずかな明暗などの小さな“ズレ”に敏感になります。
そして、そのズレを追求できる人こそが、釣果をあげることができるのです。
釣れる人は「ズレ」を探している

ベイトが多いときは、シーバスの居場所も想像しやすいです。
また、たとえシーバスの居場所がわからなくても、ベイトが多いときは回遊性シーバスに出会える可能性もあります。
しかし、ベイトが減ると、水面から得られる情報が極端に少なくなります。
そこで、釣れる人と釣れない人に差が出るのがズレを探す力です。
風の当たり方、潮のヨレ、橋脚の影、わずかな流速差など…他と違う場所を探し出せるかどうか。
釣れない人ほど、今までどおりベイトを探してしまいます。
逆に、常に釣果をあげる人ほど、目に見えにくい変化を探そうとします。
たとえば、常夜灯の光が少しだけ届かない場所や、流れがわずかに緩む場所など。
そんな小さなズレの中にシーバスの一瞬の拠りどころが隠れているのです。
釣れる人は“小さなズレ”を見逃さない
4.jpg)
ベイトが抜けたときに最も重要なのは“小さなズレ”を見逃さない力です。
潮が反転する場所であったり、風が部分的に当たらない場所であったり…
釣果をあげる人は、そうした“小さなズレ”を見逃しません。
通常の潮の流れの中から反転流にルアーが入ったその数秒後、ルアーがフッと軽くなる。
その直後、ルアーが反転しかけた瞬間にヒットする
──そんな一匹を経験した人ほど
 アングラー
アングラーといいます。
つまり、ベイトが抜けた後の釣果の差は、技術よりも観察力にあるということもできます。
広い海の中で、わずかなズレを探せる人ほど、ベイトが抜けたときでも結果を出せます。
ベイトが少ないときほど“ルアーの通し方”が効く

ベイトが抜けると、シーバスが食うタイミングはシビアになります。
ただ同じようにルアーを投げ続けるだけでは食わせられないことが多々あります。
そんなときは、ズレを探すことに加えて、「ルアーの通し方」を変えてみましょう。
同じルアーでも
・レンジを下げる
・立ち位置を変えてコースをずらす
といった感じで、小さな変化をつけましょう。
それだけで、シーバスが突然反応してくることがあります。
特に流れのある場所では、流れに逆らったトレースよりも流れに委ねたトレースのほうが効果的です。
なぜなら、ベイトが少ない中でシーバスは、違和感のない自然な動きのベイトを待ち構えているからです。
そして、それを作れるアングラーこそが、少ないチャンスをモノにできるのです。
ベイトを探すな!見えない「ズレ」を探せ!
2.jpg)
ベイトが多い時期は、ベイト主導でシーバスの動きを読むことができます。
しかし、ベイトが抜けてしまうと目に見える情報が極端に少なくなってしまいます。
そこで重要になるのが、「目に見えない海の中のズレ」です。
ベイトが減ったところで、シーバスが消えてしまうわけではありません。
少ないベイトを効率的に捕食するために、シーバスは、わずかな変化を探してベイトを追い詰めます。
そこで、ベイトが抜けた後は「ベイトを探す」のではなく「シーバスが着きそうな変化を探す」ことで、ベイトの有無に左右されず安定した釣果につなげることができます。
ベイトを探すのではなく、シーバスが「そこにいる理由」を探す。
そのわずかな変化やズレに気づけたとき、見えないベイトが想像できるようになります。
それが、ベイトのいなくても釣果をあげるアングラーの共通点です。