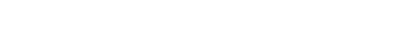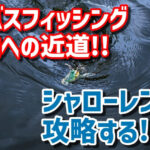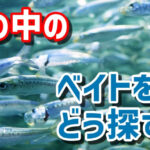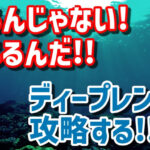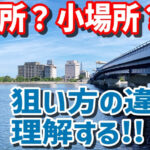ルアーを通してシーバスと向き合うとき、シーバスの習性や性格を理解することはとても重要です。
・どういう場所に生息しているのか?
・どういう性格の魚なのか?
でも、セオリーやパターンついて知って『わかった気』になっていると、釣果を伸ばすためには、中途半端な情報がかえって障害になってしまうこともあります。
このページでは、シーバスという魚の性格についてご紹介します。

最近の釣りメディアでは、釣りに関する情報がメーカーのために中・上級者目線で発信されるようになりました。ナチュラルリリースでは、ビギナー目線で語られることが少なくなった「釣りに関する『キホンのキ』」をビギナー目線で発信しています。
シーバスの性格は十匹十色
シーバスをどうやって釣るか?
これを考えるにあたって、個々のシーバスの性格を考えるようなことは普通はしません。
・あのシーバスは●●が好きだ
・そのシーバスは◇◇が嫌いみたいだ
・向こうのシーバスは△△だ
というように、個々のシーバスの性格をクローズアップすることは普通はあり得ません。
というように、普通はシーバス一括りについて考えることがほとんどです。
 ショーカラ
ショーカラでも、シーバスにも人間と同じように、個体差による性格の違いが存在します。
シーバスが10匹いれば、10匹分の性格の違いがあるといえるでしょう。
犬や猫を飼っている人にとってみれば、それぞれの犬や猫に性格の違いがあることは当然の話です。
 友人
友人みたいにひとくくりにされると
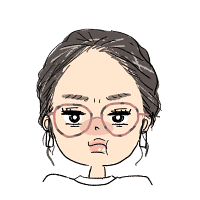 飼い主
飼い主というように、一般的に説明されるゴールデンレトリーバーの性格とはまったく違った性格の子はいくらでもいます。
シーバスも同じです。
すべてのシーバスには個体差があります。
ストラクチャーにまったく付こうとしない個体もいます。
ボトムべったりの個体もいます。
日中に積極的に活動している個体もいます。
シーバスにも個体差による性格の違いというものがあるのです。
アクアリスト目線で考えてみる
ケース①-ボトム好きのメダカ

僕は釣り以外にもアクアリウムという趣味があり、今までいろんな魚を飼ってきました。
最近ハマっているのはメダカ。
スイレン鉢に泳がせていると涼を感じられます。
メダカはスイレン鉢で飼うことが多いです。
でも、メダカをじっくり観察しようと思うと、水槽で横見をするのが一番です。
毎日水槽を覗いていると、たくさんいるメダカのうち、特定の一匹のメダカが、いつもボトムに落ちたエサをつついていることに気がつきました。
このメダカは、水面に浮いているエサにはほとんど反応せず、時間が経ってボトムまで沈んだエサをいつも食べてました。
他のメダカは、僕が水槽の前に立つと、エサだと思って水面付近まで浮上してきます。でも、その1匹だけは、常にボトムに落ちたエサを狙っていました。
ケース②-お気に入りのストラクチャー
これはメダカ以外の魚種に見られます。
魚にも好みがあって、いつも同じストラクチャーに身を寄せる個体がいます。
いろんなストラクチャーを置いても、いつも同じ場所。
逆に、いつも泳いでいてストラクチャーにはほとんど身を寄せない個体もいます。
同じ魚種なのに、性格がとても対照的な個体がいます。
ケース③-小さな体の暴君

水槽の中に同時に数匹の個体を入れると、かなりの確率で、他のメダカに攻撃を加えようとする個体がいます。
5匹のメダカを同じ水槽に入れると、1匹くらいはジャ〇アンのような性格の個体が混ざっています。
そういう個体は、自分より体の大きなメダカに対しても果敢に攻撃します。
メダカを複数匹一緒に水槽に飼っていると、1匹くらいは気性の荒い個体は存在します。
ケース④-ワイルド個体の餌付け

熱帯魚には、人工的に繁殖されたブリード個体と、現地の野生で採取されたワイルド個体と呼ばれる区別があります。
その中でも小難しい性格なのが肉食魚のワイルド個体。
基本的には、人工飼料になかなか餌付きません。
かなり頑固な個体がいて、人工飼料にまったく見向きもしてくれないことが普通にあります。
 ショーカラ
ショーカラ ショーカラ
ショーカラ逆に、エンドリケリーの別のワイルド個体は、2日目に人工飼料を食べた子がいました。
エサなんだから空腹になれば食べて当たり前…というわけにはいきません。
これは、アクアリウムの世界では常識です。
魚にだって性格の違いがあるのは当然です。
アクアリスト的な視点
水槽越しにいろんな魚の行動を観察していると、「メダカは〇〇」とか「ピーコックバスは□□」という括り方をするのは相当難しいと感じるほど、それぞれの個体の性格は違います。
「〇〇なメダカ」もいれば、それとは真逆のタイプのメダカもいます。
1匹1匹が個性をもった魚たちです。
そういう視点でみると、おそらくシーバスだって1匹1匹の性格は違うというのは当たり前といえるでしょう。
ルアーでシーバスを狙うときも、基本的にはそれぞれのシーバスの性格に合わせた狙い方というものが必要になります。
『習性』に着目したパターンフィッシング

とはいえ、いま自分の目の前にいるシーバスのそれぞれの性格に合わせてアプローチする、なんて無理ゲーです。
いま自分の目の前にいる(であろう)シーバスがどんな性格の個体か?なんて分からないし、釣りの時間が無限にあるわけでもありません。
そこで、限られた釣りの時間の中で合理的かつ効果的にアプローチする方法としてパターンフィッシングが存在しています。
シーバスのパターンフィッシングは、季節・水温・ベイトなどの条件に合わせてシーバスの行動やそのときのシーバスに効果的なルアーを絞り込んでいく戦略的な釣り方です。
つまり、パターンフィッシングは個々のシーバスの性格ではなくシーバスという魚種の習性に着目したアプローチ方法です。
すでにご紹介したとおり、個々のシーバスには個体差による性格の違いがあります。
それを前提にしつつ、もう少し大きな視点から「シーバスの習性」という共通項を見つけ出します。
シーバスの共通項を見つけ出し、それに着目してアプローチをすることで、1つのアプローチ方法でより多くのシーバスを狙うことが可能になります。
たとえば、バチ抜けパターン。
バチ抜けパターンでは、流れてくるバチを捕食するために多くのシーバスが水面を意識しています。
そこで、バチ抜けパターンでは、水面~表層付近を軽量・細身のルアーで流すように狙います。
これは、まさにシーバスの習性に着目したアプローチ方法といえます。
パターンフィッシングは、性格がそれぞれ違う魚に対する合理的なアプローチ方法であり、アングラーにとても大きなアドバンテージを与えてくれます。
パターンで釣れないときはどうする!?
パターンフィッシングが全盛になると、とにかくパターンに当てはめてアプローチをしようという風潮が生まれます。
「 バチ抜けパターンには細身の表層系ルアー」というメジャーなパターンもあれば、ある一部のプロアングラーが提唱するような〇〇パターンという名前のついていないパターンもあります。
 某プロ
某プロって感じで。
なんでもかんでもパターン化するようになります。
これは、「パターンフィッシングすべてが悪」というわけではありません。
釣りの時間は無限にあるわけではないので、アプローチ方法を合理化することはむしろ歓迎されることです。
問題なのは、
・そのパターンで釣れないときにどうするか?
ということまでフォローされているかどうか。
パターンで釣れないときに何をするか?というところまでフォローしてくれるメディアアングラーはとても少ないです。
 釣り人
釣り人 釣り人
釣り人 ショーカラ
ショーカラそんなときは原点に帰ることです。
つまり、魚には個体差による性格の違いがあるというところに帰ることです。
シーバスも1匹1匹の性格が違うことを考慮すると、当然、パターンが当てはまらない個体というのも存在します。
これは、必ず絶対に存在しているといえます。
アクアリウムの経験上、2割前後は別行動をする個体がいても不思議ではありません。
そういう場合にどうするか?といえば、原点に帰って、個々のシーバスの性格に合わせたアプローチ方法を試みる必要があります。
つまり
特定のアプローチ方法にこだわらない
ということです。
あまりにもザックリし過ぎていて答えになっていませんが…
その日・その時・その場所でどんなアプローチ方法が正解か?というのは、その日・その時・その場所にいるシーバスに聞いてみなければわかりません。
バチ抜けパターンという特定のアプローチ方法に自分のスタイルを押し込んでしまうのではなく、シーバスは個体ごとに性格が違うということを前提に、様々なアプローチ方法を模索してみましょう。
たとえば、バチ抜けパターンのときにビッグベイトを試してみるという方法もあり得ます。
あるいは、小型のバイブレーションの早巻きを試してみても面白いでしょう。
とにかく大切なのは「アナタの目の前には、いろんな性格のシーバスが泳いでいるんだよ」ということを常に頭の隅には置いておいておきましょう。
個体差を意識すれば釣りの選択肢が大きく広がる!

「パターン」や「セオリー」というのはルアーでシーバスを狙うにあたっては合理的かつ効率的なアプローチ方法です。
ただ、注意しなければならない点もあります。
それは
ということです。
犬や猫は1匹1匹の性格が違うように、シーバスも1匹1匹違う性格を持っています。
重要なのは、パターンやセオリーで釣れないシーバスがいたときに「このシーバスたちはパターンやセオリーの枠にハマらない性格のシーバスたちかもしれない」と考えられるかどうかです。
パターンやセオリーにこだわるスタイルはとても合理的です。
しかし、パターンやセオリーでしかアプローチできないとなると、釣りの選択肢はそれ以上広がることはありません。
パターンやセオリーで釣れないときこそ、原点に帰ってさまざまなアプローチ方法を試してみましょう。