
シーバスフィッシングを始めたばかりの頃。
ロッドを選ぶときに【ロッドの長さ】というのはとても問題になります。
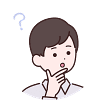 ビギナー
ビギナー15cm違うと、そんなに変わるの?
 ビギナー
ビギナーという感じで、ロッドの長さを決めるのには、かなり頭を悩ませます。
また、これらの分類に該当しないフィールドで釣りをする人はどうすればいいのか?
非常に困るところです。
 ショーカラ
ショーカラそこで、このページでは、『誰もが困らないシーバスロッドの長さの選び方』を一般論じゃない視点からご紹介します。
※ロッドの硬さについてはコチラ
今回の『企画』のきっかけ
そもそもシーバスロッドの長さを選ぶとき、どういう基準で選んでいますか?
 アングラー
アングラー アングラー
アングラーというふうに、メインフィールドをカテゴライズした基準でロッドの長さを選ぶことが一般的ではないでしょうか?
これに当てはまるフィールドで釣りをする人は、このような基準でロッドの長さを選んでも、何の問題もありません。
問題は、このフィールドカテゴライズに当てはまらないエリアで釣りをする人たち。
 ショーカラ
ショーカラ中海や宍道湖というのは、これらのフィールドカテゴライズのどれに当てはめればいいのか?
僕は全然わからなくてとても困りました。
 ショーカラ
ショーカラよくよく考えれば、シーバスフィールドというのは、日本全国津々浦々、とてもバラエティに富んでいます。
それを4つとか5つに分けてしまおうというのが、そもそも無理があるんじゃないか?
一口に港湾っていっても、漁船がひしめいて停泊している漁港や、タンカーやコンテナ船が停泊できる商港などさまざま。
これを同じカテゴリーに分類できるのか?
一般的な分類から外れたフィールドで釣りをする人はどうすればいいのか?
こういう疑問点から、ビギナーがロッドの長さを選ぶときに、なるべく迷いがなくなるようにしたいと思ったのがこの企画のきっかけです。
ここから本題
僕は、ポイント開拓とか初場所での釣りがけっこう好きです。
 ショーカラ
ショーカラこれまでも中海・大橋川・宍道湖に関しては、足場がありそうなところは、けっこういろんな場所で釣りをしました。
東京にいた頃には小規模河川メインで釣りをしていました。
もちろん、プロスタッフのように経験豊富…というわけではありません。
ただ、少ない経験ながら、シチュエーションの異なるいろんな場所で釣りをするときに、フィールドカテゴライズ方式でロッドの長さを選ぶことに限界を感じていました。
そこで、以下では、フィールドカテゴライズ方式とは違う視点から、シーバスロッドの長さの選び方をご紹介します。
絶対的基準
ベース基準―足場の高さ
◆~1m未満:8.6フィート
◆1~2m :9.0フィート
◆2m以上~:9.6フィート
足場の高さとは水面から足元までの高さのことです。
足場の高さが1m未満のフィールド(水際に立てるフィールド)では8.6ft
足場の高さが1~2mのフィールドでは9.0ft
足場の高さが2m以上のフィールドでは9.6ft
ロッドの長さを考えるときは、この長さから出発します。
付加ファクター①―遠浅のフィールドか?
遠浅のフィールドとは、たとえば、自分の立ち位置から30mくらい沖に出ても水深が50cmくらいしかないようなフィールドのことです。
このような遠浅のフィールドでは、ベースの長さに+0.6~1.0ftします。
遠浅のフィールドじゃないときはベースの長さのまま(±0)です。
付加ファクター②―テイクバックスペースがあるか?
自分が釣りをするメインエリアが、ロッドを振りかぶるのに十分なスペースがあるか?
ということです。
ロッドを振りかぶるスペースが十分にあるときは±0です。
ロッドを振りかぶるのが窮屈なときは-0.6ftとします。
裁量基準
裁量ファクター③―オープンエリアか?
◆ストラクチャー「も」撃つ ±0
◆ストラクチャー撃ちがメイン -0.6~1.0
◆オープンでもストラクチャー撃ちでもない ±0
釣りをするメインエリアがオープンエリアで、ピンポイントにキャストすることがほとんどないときは+0.6ftします。
場合によってはストラクチャーを撃つこと「も」あるときは±0です。
ストラクチャー撃ちメインという場合には-0.6~1.0ftします。
ストラクチャー撃ちはしないけど、メタルジグをフルキャストすれば対岸まで届くかもしれないって感じの場所がメインフィールドの場合には±0です。
裁量ファクター④―飛距離が「特に」必要か?
飛距離が「特に」重要なファクターになるフィールドでは+0.6~1.0ftします。
シーバスフィッシングでは、「飛距離が必要ない」場所がメインフィールドの人は、それほど多くないでしょう。
そこで、ここでは「特に」必要といえるときに限り長さを長くします。
裁量ファクター⑤―ディープウェーディングをする
腰からお腹あたりまで水に浸かって釣りをするスタイル(ディープウェーディング)の場合、ロングロッドだとキャスト時にロッドティップ(竿先)が水面を叩くことになります。
そこで、ディープウェーディングスタイルの釣りメインのときは-1.0ftします。
絶対的基準の説明
絶対的基準とは、言い換えれば、釣り場で課されることになる制約(制限)です。
【足場の高さ】【遠浅かどうか】【立ち位置の背後の状況】というファクターは、自分の力ではどうにも変えることのできないシチュエーションの問題です。
釣りをするうえでは、これらによって課される制約は受け入れる必要があります。
そこで、ここに掲げた絶対的基準は、①→②→③の順番に必ず検討することになります。
ベース-足場の高さについて
ロッドの長さ選びの基準の中で最重要かつ最優先基準になるのが【足場の高さ】です。
シーバスに限らず、ほとんどの釣りにおいて、ロッドの長さが最も影響する状況は足元での魚とのやりとりです。
足場が高いのにロッドが短いと、足元で魚をコントロールすることがとてもやりづらいです。
反対に、水辺に立って釣りをしているのにロングロッドを使っていると、魚の取り込みにモタモタするようになります。
ロッドの長さを選ぶうえで最重要ファクターが【足場の高さ】です。
遠浅のフィールドか?
メインフィールドが遠浅の場合、バイブレーションなどの沈みやすいルアーを手前まで引いてくると、手前でルアーが根掛かりすることが多くなります。
根掛かりしないまでも、ルアーのフックが海藻を拾いやすくなったりして、けっこう煩わしいものです。
遠浅のフィールドにおいて、手前(岸に近い場所)でルアーをさばこうとしたとき、ショートロッドだとどうしてもルアーを操作しにくくなります。
遠浅のフィールドでは長めのロッドの方が有利になるので+0.6~1.0ft必要になります。
バイブレーションのような沈みやすいルアーを使うことはほとんどないでしょうから、手前でのルアーの操作が問題になることはほぼないでしょう。
テイクバックスペースがあるか?
メインフィールドが、ロッドをしっかりと振りかぶることができる場所であれば無視してもいいファクターです。
テイクバックが窮屈であったり、後ろまで振りかぶるスペースが少ないようなときは-0.6ftにします。
 ショーカラ
ショーカラ「短いロッドの方が明らかに投げやすい!」という場所がメインフィールドの場合、ベースの長さよりも短いロッドにします。
裁量基準の説明
裁量基準とは、釣り場のシチュエーションや釣りのスタイルに合わせて検討すべき項目です。
これに該当する場合であってもこのファクターを考慮するかどうかの最終判断がアングラーに委ねられる基準です。
つまり、ベース→①→②という流れでロッドの長さを検討したあとの微調整のための基準です。
裁量基準なので、これを考慮するかどうかは最終的にはアングラーの裁量にお任せします。
ただ、シーバスビギナーで「ロッドの長さを選ぶ基準が全然わからないよ!」ってときは裁量基準をすべて考慮・検討してもらった方がいいでしょう。
オープンエリアか?
個人的には、【足場の高さ】の次に重要になるファクターが【オープンエリアでの釣りかどうか】だと考えています。
シーバスフィッシングは飛距離がとても重視される釣りです。
その理由の一つとして、かなり多くのシーバスフィールドがオープンエリアということが挙げられます。
これが多くのアングラーの一般的なスタイルです。
目標物のないオープンエリアで釣りをする場合には飛距離はとても重要になります。
そこで、ベースのロッドの長さよりも+0.6ftします。
オープンエリアでも釣りをするし、ストラクチャー撃ちのピンポイントキャストもする。同じくらいの割合でどちらの釣りのスタイルも可能性がある、というときは±0にします。
また、ストラクチャー撃ちがメインという人は、短いロッドの方が圧倒的にキャストしやすいので-0.6ftします。
ストラクチャー撃ちをするわけではないけど、フルキャストすれば対岸まで届くかもしれない、という感じのいわゆる『小場所』がメインフィールドの場合は±0です。
飛距離が「特に」必要か?
飛距離が「特に」必要な場合とは、一つはフィールドによって求めらることがあります。
サーフや大規模河川などがその典型です。
これらのフィールドがメインフィールドの場合、+0.6~1.0ftを考えましょう。
ほかにも、飛距離が「特に」必要な場合として、「ビギナーだからキャストに慣れていない」という場合があります。
ロングキャストする必要があるけど、まだキャストに慣れていないというビギナーの場合、ロッドの長さに助けてもらう必要があります。
その場合には+0.6~1.0ftを考えましょう。
この「キャスト慣れしていないビギナー」の場合は、さらに考慮要素として「どういうルアーをメインで使うか?」を考えましょう。
たとえば、メインルアーがバイブレーションやメタルジグの場合。
これらのルアーは、ビギナーであっても比較的飛距離が出しやすいルアーたちです。
そこで、この場合には、±0でもいい(+0.6~1.0ftしなくてもいい)ですし、せいぜい+0.6ftで十分でしょう。
しかし、メインルアーがミノーのような場合。
この場合、短いロッドで飛ばすには慣れが必要なので、キャストに慣れないうちは+0.6~1.0ftをして、ロッドの長さに助けてもらいましょう。
ディープウェーディングをするか?
シーバスフィッシングでは、腰くらいまで水に浸かるディープウェーディングもそれほど珍しいスタイルではありません。
ディープウェーディングをするようなエリアはオープンエリアが多く、飛距離が必要になることも多いです。
そのため、ビギナーの頃は「ロングロッドの方がいいのでは?」と考えがちです。
でも、ディープウェーディングでロングロッドを使う場合、慣れていないとキャストのときに竿先が何度も水面を叩くことになります。
なので、シーバスビギナーの頃にディープウェーディングをする場合、ロングロッドはおすすめしません。
ディープウェーディングをする場合には-1.0ftにします。
膝くらいまでのウェーディングであれば±0です。
 ショーカラ
ショーカラロッドの長さの選び方(まとめ)
絶対的基準
◆~1m未満:8.6フィート
◆1~2m :9.0フィート
◆2m以上~:9.6フィート
◆遠浅のフィールド +0.6~1.0
◆後ろのスペースが狭い -0.6
裁量基準
◆オープンエリアでの釣り +0.6
◆ストラクチャー「も」撃つ ±0
◆ストラクチャー撃ちがメイン -0.6~1.0
◆オープンでもストラクチャー撃ちでもない ±0
◆飛距離が「特に」必要 +0.6~1.0
◆ディープウェーディングをする -1.0
結果
ロッドの長さを選ぶときは、まずはベースの長さから決めます。
つまり、自分が釣りをする場所の足場の高さ・手前の水深(①)・背後のスペース(②)を考えます。
足場の高さを基準にベースの長さを決めたあと、①と②から割り出された長さをプラスします。
その後、ロッドの長さを微調整するために③・④・⑤を検討します。
③・④・⑤を考慮するかどうかはアングラーの皆さんの経験によるところが大きいです。
ただ、こういう説明をするとビギナーの方々は困るかもしれません。
そこで、そもそもロッドの長さ選びに困っているビギナーの頃は、すべてのファクターを考慮・検討してみましょう。
具体例で考えてみよう!
遠浅ではないサーフ
サーフの釣りは水際で釣りをすることになります。
足場の高さ基準によれば、サーフの釣りのベースの長さは8.6フィートです。
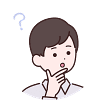 ビギナー
ビギナーと考えるかもしれません。
でも、足場と水面の高さが同じなので8.6ftがベースです。
ファクター② ±0
サーフでも、遠浅でなければ①は±0です。
また、サーフの場合、テイクバックのスペースに困るということはないでしょうから、②も±0です。
つまり、遠浅じゃないサーフの場合、絶対的基準では8.6ftがベースになります。
ファクター④ +0.6~1.0
ファクター⑤ ±0
サーフの釣りはオープンエリアの釣りになるので③は+0.6です。
また、サーフは、飛距離が「特に」必要といえる場合がほとんどなので、④は+0.6~1.0です。
最後に、サーフではウェーダーを履くとはいえ、ディープウェーディングをするようなことはほぼないでしょう。
そこで、⑤は±0です。
8.6+0+0+0.6+0.6(~1.0)+0
結論として、遠浅ではないサーフの場合、ロッドの長さは9.6~10.0ftくらいで決めてもらえばOKです。
沖堤防
沖堤防(沖波止)は足の高さが高い場所が多いので、ベースの長さは9.0~9.6になる場合がほとんどでしょう。
ファクター② ±0
次に、沖堤防が遠浅ということは通常は考えられないので、①は±0です。
また、沖堤防は人が多くてもバックスペースは十分に確保できる場所が多いので、②も±0です。
ファクター④ +0~0.6
ファクター⑤ ±0
沖堤防はオープンエリアの釣りになるので、③は+0.6です。
沖堤防の釣りで迷うところが④です。
基本的にはかなりのオープンエリアでの釣りになるのでルアーを飛ばせることに越したことはありません。
でも、沖堤防で使うルアーといえば(メタル)バイブレーションやメタルジグのようなそもそも飛距離の出るルアーを使う場合がほとんどです。
そうなると、④については±0あるいは+0.6で十分かな?というのが僕の考えです。
沖堤でウェーディングすることはあり得ないので、⑤は±0です。
結論として、沖堤防では9.6~10.6ftの範囲で決めてもらえばOKです。
ロッドの長さを考えるときの注意点
上の具体例では、シチュエーションをイメージしやすいように『サーフ』とか『沖堤防』というカテゴライズをしました。
しかし、実際にロッドの長さを考えるときには、シチュエーションをカテゴライズする必要はありません。
ロッドの長さを考えるときは、あくまでご自身のメインフィールドの具体的なシチュエーションをあてはめて考えます。
ということをチェックしてください。
「サーフだから●ft」とか「沖堤防だから●ft」とか「河川だから●ft」という大雑把なカテゴライズは必要ありません。
具体的な足場の高さ・水深・バックスペース・釣りのスタイル等について、ご自分のメインフィールドにあてはめて検討してください。
まとめ
ここでご紹介したシーバスロッドの長さの決め方は、決して一般的な分類ではありません。
シーバスロッドの長さの決め方の一般的な考え方は、自分のメインフィールドを「港湾」とか「河川」とか「サーフ」というカテゴライズして、そのフィールドに合った長さから選ぶというものです。
しかし
 ショーカラ
ショーカラというアングラーも少なからず存在しているでしょう。
そういうときは、とりあえず騙されたと思って、ここでご紹介したロッドの長さの決め方で考えてみてください。
そのとき、ポイント状況が分かるようにポイントの写真なんかを添えていただければ、より助かります。
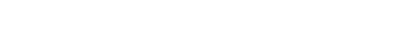



-150x150.jpg)

