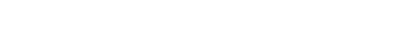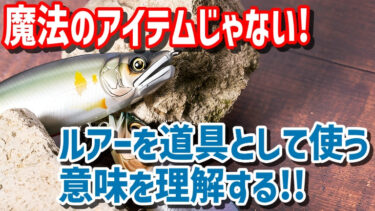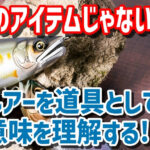第26回の記事でルアーを「道具として使う」ことについておおざっぱに説明しました。
このページでは、道具であるルアーの具体的な使い方についてご紹介します。
ナチュラルリリースではビギナー向けにシーバスフィッシングの初歩の初歩をご紹介しています。その中で、何度も登場するのが・ルアーはエサではない・ルアーは魚を勝手に引き寄せてくれる魔法のアイテムでもない・ルアーはただの道具[…]
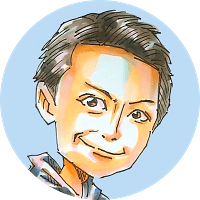
最近の釣りメディアでは、釣りに関する情報がメーカーのために中・上級者目線で発信されるようになりました。ナチュラルリリースでは、ビギナー目線で語られることが少なくなった「釣りに関する『キホンのキ』」をビギナー目線で発信しています。
「道具として使う」って具体的にどういうこと?
ここ20年くらいでシーバスルアーの種類は劇的に増えました。
それに伴って、ルアーのカテゴリーの細分化も進みました。
「●●の状況ではこのルアー」とか「ベイトが○○のときはこのルアー」という感じで、1つのルアーにつき1シチュエーションのような状況になっています。
ところで、ルアーのことはいったん置いておいて、工具であるマイナスドライバーについて考えてみましょう。

みなさんがマイナスドライバーを使うのは、どういう状況でしょうか?
もちろん、マイナスネジの締緩のときです。
でも、それだけではありません。
ドライバーの先端がハマるのであれば、プラスネジの締緩に使うこともあります。
ほかにも、マイナスドライバーを蓋の隙間に差し込んで、蓋をこじ開けたりするときにも使います。
つまり、マイナスドライバーは、マイナスネジの締緩に限られず、マイナスドライバーが役立つ状況であればいろんな場面で使用することができます。
これは、ルアーについても同じことがいえます。
ルアーというのは魚を釣るための機能を備えた道具です。
その機能が役に立つ状況であれば、どんな場面で使用しても間違いではありません。
ルアーに備えられた機能が役立つ限り、さまざまな場面で使うことができるのです。
これがルアーを「道具として使う」という意味です。
ルアーの用途はなぜ限定されてしまうのか?
マイナスドライバーであれば、ほとんどの人が、他人から言われなくてもさまざまな用途に使います。
しかし、ルアーに関していえば、(特にビギナーの場合は)用途を限定してしまう方向にあります。
それはなぜか?
一つはメーカー戦略があります。
最近は、新製品のルアーについて、メーカーのスタッフがそのルアーの使い方を動画などで配信しています。
このようなレクチャー動画を見た多くのビギナーは、スタッフのレクチャーする使い方に引っ張られてしまいます。
 某プロ
某プロという説明を聞けば、ビギナーであれば同じ使い方をするのが普通でしょう。
もう一つの理由は「魚に食いつかせる機能」が重視されてきたことです。
前の記事でご紹介したとおり、「魚を惹きつける機能」や「魚に食いつかせる機能」というのは、ルアーの機能の中では客観的に判断できない機能です。
そして、よくわからない機能である以上、その機能を使い分けたり応用したり…ということもできません。
この「よくわからない機能」が重視されてきた結果、ルアーをいろいろなシチュエーションで活用するというルアー本来の「道具としての使い方」が語られることなく、ルアーの用途が限定的になっていきました。
シンプルな思考でルアーを活用してみよう!
「魚に食いつかせる」というよくわからない機能はとりあえず置いておいて…
客観的にわかりやすいルアーの機能に着目して、もっとシンプルな思考でルアーを活用してみましょう。
シャッドの代わりにバイブレーションを使ってみる
.jpg)
たとえば、橋脚をピンポイントで狙ってみたい場合。
シャッド・ミノー・シンキングペンシルなどで、クイックorスローにアプローチしていくのが一般的でしょう。
でも、橋脚までの距離があるため、シャッドやミノーで狙いにくい場合はどうすればいいのか?
単純に、橋脚まで届くルアーを使うことになります。

たとえばバイブレーション。
バイブレーションなら、シャッドやミノーが届かないスポットにも到達できます。
また、バイブレーションならシンキングペンシルでは到達できない深めのレンジまでルアーを送り込むことができます。
バイブレーションは、遠投して広範囲にサーチするために使われることが多いルアーであることはいうまでもありません。
しかし、シャッドの代わりにピンスポットを狙うために使っても、まったく間違いではありません。
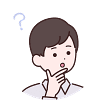 ビギナー
ビギナーという疑問もあるかもしれません。
もちろん、その可能性は充分に考えられます。
でも、食わせられるとか食わせられないというのは、ルアーの機能の中では客観的に判断するのが難しい機能です。
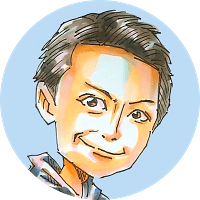 ショーカラ
ショーカラわからないことを心配するよりも、魚の居る場所・自分の狙いたい場所・狙いたいレンジにルアーを届けることのほうを優先すべきです。
遠投用のシンキングペンシルを近距離で使ってみる
遠投のために作られたシンキングペンシルだからといって、遠投しなければならないわけではありません。
20m程度の近距離でアプローチするために、ぶっ飛びシンキングペンシルを使うこともあります。

たとえば、この2つのシンキングペンシル。
上が汎用シンキングペンシル。下がぶっ飛びシンキングペンシルです。
そもそも、20m程度であればBANQ(写真上)でまったく問題なく狙うことができます。
じゃあ、何のためにぶっ飛びシンキングペンシルを短距離で使うのか?
この場合に注目するルアーの機能は、ルアーの飛距離ではなくルアーの重さです。
BANQ82Sは14gですが、ヘビーショット85Sは20gです。
同じスピードでシンキングペンシルを引いたとき、ルアーの重さが変われば、ルアーのレンジも変わります。
同じスピードでルアーを引いた場合、当然ですが重いシンキングペンシルの方が深いレンジを引いてくることになります。
つまり、スピードを変えずにより深いレンジを探りたいのであれば、短距離を狙う場合であっても重量のある遠投用のシンキングペンシルが活躍します。
このように、客観的に区別可能なルアーの機能に着目すると、それぞれのルアーが活躍できるシチュエーションを、シンプルな思考で広げることができます。
ルアーの機能を活かしてルアーが活躍できるシチュエーションを広げてみよう!

ルアーは、エサの代替品ではありません。
魚を釣るための機能を備えた道具
それがルアーです。
その道具の機能が役立つ状況であれば、どんな状況で使ったとしても間違いではありません。
ルアーの用途を特定の状況に限定するのではなく、ルアーの機能を活かして様々なシチュエーションで活用してみましょう。