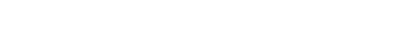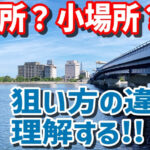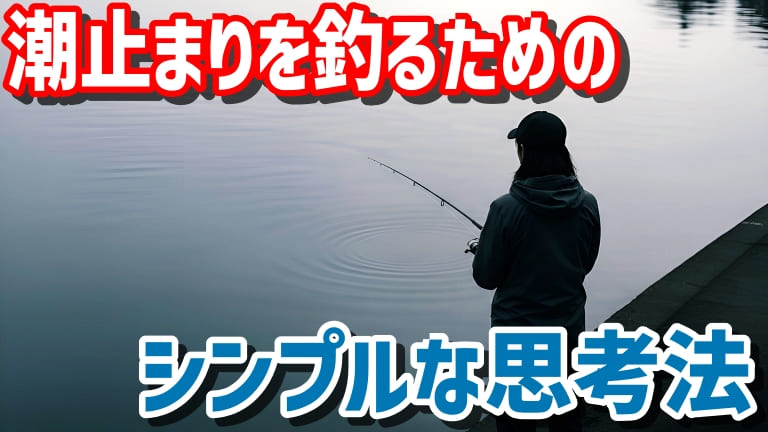
潮が止まった瞬間、海も釣り人も静かになります。
ベイトの波紋が消え、ラインもたるみ、心のテンションも緩みます。
「いまの時間帯はダメか…」
と感じる方も多いでしょう。
とはいえ、シーバスが海の中から消えることはありません。
また、潮流というのは捕食の絶対条件というわけではありません。
そのため、「潮止まりのときは本能的に捕食しない」というわけではありません。
そこでこのページでは、潮止まりをチャンスに変えるためのシンプルな思考についてご紹介します。
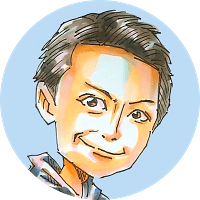
最近の釣りメディアでは、釣りに関する情報がメーカーのために中・上級者目線で発信されるようになりました。ナチュラルリリースでは、ビギナー目線で語られることが少なくなった「釣りに関する『キホンのキ』」をビギナー目線で発信しています。
FAQ(よくある質問)

潮止まりで釣れない理由
2.jpg)
潮止まりでシーバスが口を使わなくなる背景には2つの大きな理由があります。
流れが止まるとベイトが散る
潮が動いているときは、プランクトンや小魚が潮の流れに乗って集まります。
その結果、ベイトの濃いエリアが生まれます。
しかし、潮止まりになると、この流れが止まってベイトは散ってしまいます。
ベイトが散ると、これを捕食しているシーバスも散ってしまい、シーバスを狙うときの効率が下がります。
結果として、シーバスの活性が落ち、ルアーへの反応も鈍くなったと感じるようになります。
シーバスなどの回遊ルートが消える
シーバスは潮の流れに沿って移動します。
つまり、潮流自体が“シーバスの回遊ルート”の役割を果たしています。
ところが、潮が止まるとこの回遊ルートがなくなり、シーバスの動きが一定ではなくなります。
シーバスの移動が一定でなくなる結果、潮流を狙った回遊待ちの釣りが成立しにくくなります。
そのため、同じ場所で粘っても釣果を得にくくなるのです。
シーバスが消えるわけではない

ここで重要なのは
②そもそも潮流は捕食活動の絶対条件ではない
ということ。
この発想はとても重要です。
たとえば、水族館で飼育されているスズキが典型です。
スズキという魚は、多くの水族館で飼育されています。
しかし、水族館の水槽内は、水流は発生させることができても、月の引力による潮流を発生させることはできません。
とはいえ、潮流はなくてもスズキは給餌されたエサを捕食します。
つまり、シーバスの捕食に関していえば、潮流というのは本能的な条件ではないということです。
したがって、海にシーバスが残っている以上、潮止まりといえどもシーバスを釣るチャンスが必ずあるということです。
ここで重要なのは、漫然とシーバスを待つのではなく「シーバスがいる場所を探す」という視点に切り替えることです。
潮止まりを釣るためのシンプルな思考法
2-1.jpg)
潮止まりでもシーバスは海のどこかに残っています。
そして、潮流の有無はシーバスの捕食にとって絶対条件というわけではありません。
そこで重要になるのがわずかにでも水が動いている場所を探すということです。
つまり“ポイントを絞るための引き算”です。
無理にシーバスを引き出すのではなく、シーバスがいそうにない場所を除外し、残ったポイントに全集中することです。
オープンエリアは除外する
オープンエリアは、潮が動いているときはルアーがよく流されますが、潮止まりのときはルアーが真っ直ぐ帰ってきます。
このようなときは、ベイトやシーバスの回遊ルートを限定しづらくなります。
そのため、潮が動いていないときはオープンエリアは見切りましょう。
シャローエリアも条件付きで除外する
流れのないシャローエリアは、ベイトが溜まっているときはボイルが頻発することがあります。
しかし、ベイトが溜まっていなければ、潮止まりにシーバスが回遊してくる可能性はかなり低いエリアといえます。
そこで、ベイトが溜まっていないシャローエリアも除外しましょう。
小規模河川・工場排水・農業用水の流れ込みを探す
海全体の流れが止まっているように見えても、わずかに水が動いている場所があります。
それが小規模河川・工場排水・農業用水の流れ込みです。
プランクトンや小魚は、こうした水の動きのある場所に集まることが多いです。
つまり、小魚やシーバスはこのようなわずかな変化でも敏感に感じ取っているのです。
潮止まりで海全体の流れがないときは、水の動かない場所は除外して、小さな水の動きを探しましょう。
移動も“引き算”で考える
潮止まりで反応がないときは、焦ってあちこち移動するのではなく“動いている水”をピンポイントで探して効率的に移動することも大切です。
最近はスマートフォンでいつでもGoogleマップにアクセスできるので、河川の流入エリアを探してみましょう。
水が大きく動くエリアを無理に探すのではなく、「わずかでも動いていそうな流れ込み」を見極めて移動します。
実際に潮止まりに小規模河川の河口エリアに行ってみると、オープンエリアよりもはるかに生命感に溢れていることがあります。
そういった小さなヒントの先にシーバスは潜んでいます。
釣れない時間を情報収集にあてる
潮止まりの時間でどうしても釣れない時間帯は、観察の時間として活用してもいいでしょう。
水の動き、ベイトの反応、風の向き、明暗の位置…
少しでも変化がある場所を探しておくと、次に潮が動いた瞬間、その場所が一気に“爆釣ポイント”になることがあります。
「潮止まりだから釣れない」とあきらめず、自然を観察する時間にあてましょう。
それが、次の一本につながります。
回遊の可能性の低いエリアを除外しよう!
1.jpg)
潮止まりでも、シーバスは海のどこかに残っています。
また、潮の流れはシーバスの捕食トリガーの絶対条件ではありません。
重要なのは、「待ちの釣り」から「シーバスがいるエリアを見つける釣り」に視点を切り替えることです。
そこで効率的にポイントを絞るのが“ポイントの引き算”です。
魚がいない場所を除外する
わずかでも水の流入のあるポイントに絞る
最大限に観察する
この“ポイントの引き算”が潮止まりでも釣果を生む最短ルートです。
潮が止まっても、シーバスは消えません。
ただ、ベイトやシーバスの回遊ルートを絞りづらくなるだけです。
そこで、ベイトやシーバスが居そうな場所を探すことに集中しましょう。
静かな海には、静かな答えがあります。
それをいかに探し出せるかが、潮が動かないときに釣果を出すためのポイントです。