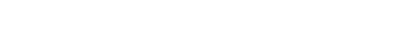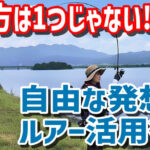シーバスルアーの中で不人気カラーの代表といえる「ブラック系」。
釣具店ではブラック系のルアーは売れ残りがちで、「地味で釣れなさそう」と敬遠されるカラーです。
売れないがために、メーカーも積極的にはブラック系のカラーをラインナップには加えません。
しかし、実際のところ、シーバスのナイトゲームでは定番カラーというべき「ブラック系」。
ベテランアングラーほどブラック系をよく使い、釣果を上げています。
昔から「夜はブラック系が効く」といわれていて、個人的にも「当たり前のように釣れる」という認識です。
とはいえ、その理由をしっかり理解している人は意外に少ないかもしれません。
なぜ、ブラック系はナイトゲームで効果的なのか?
このページでは、シーバスの感覚器官に着目して、ブラック系カラーの使い方についてご紹介します。
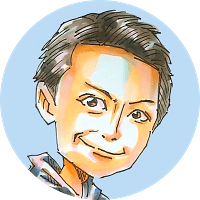
最近の釣りメディアでは、釣りに関する情報がメーカーのために中・上級者目線で発信されるようになりました。ナチュラルリリースでは、ビギナー目線で語られることが少なくなった「釣りに関する『キホンのキ』」をビギナー目線で発信しています。
なぜブラック系は敬遠されがちなのか?

釣具店のルアーコーナーを見てみましょう。
売れ筋はチャート・パールホワイト・レッドヘッドといった膨張色。あるいは、イワシ・ボラ系のナチュラルカラーです。
他方で、ブラック系ルアーはそもそもラインナップになかったり、あったとしても在庫として残りやすく、不人気カラーの代表といえます。
その理由はいくつかあります。
まず1つが“シンプルすぎる”というもの。
煌びやかなカラーがたくさんあるのに、なぜ、油性マジックで塗ったようなカラーを選ぶ必要があるのか?
ということです。
 ビギナー
ビギナー2つめが“魚っぽくない”というもの。
最近では強鱗、アデル、ライブベイトといった超リアル系カラーがたくさんあります。
にもかかわらず、単色ブラック系をあえて選ぶという選択肢があるでしょうか?
3つめが魚っぽくないから“釣れなさそう”というもの。
これは、消費者心理というよりもアングラー心理というべできしょうか。
誰がどう考えても、リアルっぽいカラーの方が釣れそうだし買いたくなります。
そして4つめが“ナイトゲームでは見えないでしょ?”というもの。
ここ15年くらいでシーバスのデイゲームが飛躍的に開拓されました。
とはいえ、日中に仕事や学校があるアングラーにとって、やはり主戦場はナイトゲーム。
 アングラー
アングラーというのはアングラーの心理として理解できます。
このような理由から、地味なブラック系には手が伸びにくいのが実情です。
視覚構造とブラック系のシルエット効果
じゃあ、「ブラック系はナイトゲームでは使えないのか?」といわれると、そんなことはありません。
むしろ、シーバスにとって強烈に作用するシチュエーションがあります。
シーバスの目の構造

スズキ(シーバス)の目には、光を感じ取る桿体細胞(かんたいさいぼう)が多数分布しています。
桿体細胞は暗所での感度が非常に高く、わずかな光量でも視覚情報として捉えることができるそうです。
そのため、シーバスは、夜間のような光量の少ない時間・場所でも周囲を把握することができ、暗所での捕食行動に適応していると考えられています。
つまり、シーバスの目は、夜の海でも周囲をしっかり認識できる夜行性仕様の目になっているということです。
そのためシーバスは、真っ暗闇でない限り、夜でも視覚を使って獲物を捕食することができます。
ブラック系のシルエット効果

月明かりや常夜灯がある場所では、光(月明かり)と影(ルアーのシルエット)のコントラストが生まれます。
『光』である月明かりや常夜灯に対して、ブラック系ルアーのシルエットは『影』としてシーバスの目に強烈に浮かび上がるのです。
月明かりや常夜灯の効いた河川や港湾部では、ブラック系のミノーやシンペンが逆光の中でくっきりとシーバスの目に映るため、ナチュラルカラー以上の効果を発揮することがあります。
また、フラッシング系のルアーが見切られる状況でも、ブラック系なら長く見せられます。
月明かりほどの光があれば、ブラック系のカラーのシルエット効果は大きな武器になります。
光量がほとんどない状況でのブラック系

では、光量がほとんどない場所ではどうでしょうか?
このようなシチュエーションでは、ブラック系ルアーが「視覚的にシルエットを見せる」という効果は薄れてしまいます。
それでもブラック系で当たり前のように釣れるのは事実です。
その理由については2つの可能性が考えられます。
1つは「人間の目には真っ暗でも、シーバスの目にはわずかな光を利用して見えている」こと。
もう1つは「視覚のほかにも、側線を活用して感知している」ことです。
どちらが優位かを断定するのは難しい問題です。
一応、ブラックバスを使った実験では、視覚が優位という研究結果があるようです。
また、側線で感知できる水の動きは体から数十cmほどの範囲(側線の感知能力の高い魚で1mくらい)ということを考えると、夜行性のシーバスが側線で獲物を探すのはかなり非効率のように思えます。
ただ、いずれにせよ、真っ暗闇でもシーバスは何らかの方法でルアーを認識して捕食しているのは確実です。
そこで、光量のない状況ではブラック系はナチュラル系のカラー(見切られにくいカラー)として捉えておくといいでしょう。
光量別のブラック系ルアーの使い分け
ここまでの話で、ブラック系は、万能ではないにしろ状況によって効果的なカラーだということができます。
そこで、下記のように整理して、ブラック系ルアーを活用することができます。
光量がある場合(月明かり・常夜灯)
.jpg)
わずかな光があれば視覚が優位に働きます。
ブラック系は、シルエットは際立ちますが、不必要にシーバスの視覚を刺激しないため、見切られにくいといえます。
常夜灯周辺・橋脚周り・月明かりのある場所では、シーバスの視覚にアピールでき、かつ、見切られにくいカラーとして主戦力になり得ます。
光量がない場合

ブラック系のカラーだけでは視覚的に目立ちにくくなります。
そこで、膨張色(パールホワイト・チャート)でシルエットを見せた方が効果的です。
ブラック系を使うなら、アクションの大きなルアーで視覚と側線に働きかけることを意識したほうがいいでしょう。
朝夕マズメ

夜の月明かりでも見えるくらいなので、朝マズメや夕マズメ程度の光量があれば充分すぎるくらい視覚が働きます。
光量が少なくなればなるほど、ブラック系はナチュラルカラーとして効果を発揮します。
朝夕マズメ時、フラッシングを警戒するシーバスに対してはとても有効です。
ブラック系をどう使いこなす?

ブラック系はシーバスに強烈に効く場面がはっきり存在します。
だからこそ、知っている人だけが釣果を伸ばせる“裏カラー”でもあるのです。
とはいえ、ブラック系を使ったことないビギナーは、「ブラック系から入る」より「ブラック系で締める」という感覚を持っていたほうが、使用上、気持ちのハードルが下がるはずです。
・光量がない場所では“警戒心を和らげるナチュラルカラー”としてブラック系を補助的に使う
・「ブラック系から入る」より「ブラック系で締める」という感覚で使う
実は効果的!使いどころがわかれば武器になる!!

ブラック系は不人気カラーの代表といえるカラーです。
しかし、視覚的に、アピール系とナチュラル系の両方からシーバスにアプローチできる、とても奥深いカラーです。
・光量がない → 側線で感知している可能性もある。ナチュラル系と捉えて、膨張色との使い分けが重要
光量に着目して使い分ければ、ブラック系は信頼できる武器になります。
ブラック系を避けるか?
それとも、ブラック系を武器にするか?
その選択が、ナイトゲームの釣果に大きな差を生み出します。