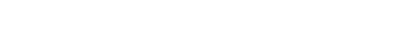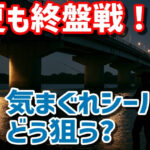例年であれば、11月後半は海も空気もすっかり冬支度に入り、水温は10℃台前半へ向かい始める時期です。
ベイトは抜け、シーバスは深場や越冬ポイントへ移動し、秋の高活性な釣りは一区切り…
そんなイメージを持つ方も多いでしょう。
しかし、今年は様子が違います。
沿岸部の水温は15℃前後を保ち、海の中にはまだ“秋の名残り”がしっかり残っています。
その結果、シーバスの行動も例年とは少しズレた、独特な変化を見せ始めています。
このページでは、水温が下がらない晩秋のシーバス攻略法についてご紹介します。
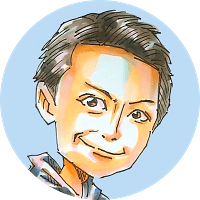
最近の釣りメディアでは、釣りに関する情報がメーカーのために中・上級者目線で発信されるようになりました。ナチュラルリリースでは、ビギナー目線で語られることが少なくなった「釣りに関する『キホンのキ』」をビギナー目線で発信しています。
FAQ(よくある質問)

秋が残るとシーバスはどう動く?

表層~中層の回遊が続く
15℃前後は、シーバスにとってまだまだ動きたい水温です。
冬のように底ベッタリにならず、ハイシーズンとほぼ同じレンジを回遊します。
特に回遊しやすいのは以下の自然条件のときです。
・小潮~長潮の潮の動かない日
・ベイトが薄く散在するエリア
これらの条件下では、表層~中層をフラフラと回遊するシーバスが残り、秋の釣りをそのまま当てはめやすくなります。
ベイトの抜けが遅れる
例年なら、11月になると何度か急激な気温の低下が起こり、徐々に水温も低下していきます。
この水温の低下により、一気にベイトが動き始める(抜ける)タイミングが生まれます。
しかし、水温が高いと、ベイトの魚影が薄くなりつつも依然として居残りベイトがいるため、これを狙うシーバスにもポツポツと遭遇することがあります。
シーバスの回遊は散発的になりやすい
水温が高いとはいえ、体の小さなベイトたちは水温低下による影響をシーバスよりも早く感じます。
このため、秋のような大規模なベイトの回遊は発生しにくく、小規模な群れが点在している状態になります。
これにより、ボイルは小規模で単発的なものになり、活性の上がるゴールデンタイムも短時間なものになりやすいです。
このように、水温が高い状態が続くと、水中の四季の変化を読みづらい状況が生まれます。
晩秋でも通用する“秋の延長の”ルアー選び
ミノー(90~120mm)
1.jpg)
水温が高い晩秋の主力ルアーは100mm前後のミノーです。
表層~中層を効率よく直撃することができ、サイズ感も秋のベイトにピッタリです。
特に効きやすいのはややスロー~ミディアムなタダ巻きです。
潮流の強い場所をスローに通すことで、オートマチックにバランスを崩し、魚影の薄いベイトを追ってフラフラと回遊しているシーバスにアピールすることができます。
シンキングペンシル(90mm前後)
1.jpg)
魚影の薄いベイトを追ってフラフラと回遊しているシーバスに非常に強いのがシンキングペンシルです。
沈めすぎず、表層付近をフラつかせながら漂わせることで、これを見つけたシーバスの捕食トリガーに働きかけます。
風の弱い日にデッドスローで水面付近を通していると、水面を割って出てくることさえあります。
風が落ち着いたタイミングでシンキングペンシルをスローに通すととても効果的にシーバスにアピールできます。
軽めのバイブレーション(15g前後)

デイゲームの切り札がバイブレーションです。
ボトムをゴリゴリと通すよりもボトムから数十cm上のレンジを引き抜くイメージで狙うと反応が出やすいです。
また、バイブレーションは、ボトムのベイト(ハゼ・カニ・虫系ベイト)を意識したシーバスも拾うことができます。
デイゲームの切り札として必ず準備しておきましょう。
ナイトゲームでの狙い方
1.jpg)
ベイトがいればベイトに合わせる
11月後半といえ、水温が15℃前後もあれば十分にベイトが活発な水温です。
そのため、表層付近にベイトの存在が確認できるときは、通常どおりルアーのサイズやレンジをベイトに合わせて狙いましょう。
ベイトがサヨリであれば、かなり水面に近いレンジで勝負します。
ベイトがボラであれば、120mmクラスのシャローランナーやミノーでアプローチします。
つまり、ベイトの存在が確認できるときは普段どおりにシーバスを狙いましょう。
ベイトの存在が確認できないとき
反対に、ベイトの存在が確認できないときは、無理にベイトを探すのではなく“水中のズレ”を探します。
・護岸の変化によって生じる反転流
このように、ベイトが溜まりそうな場所を愚直に狙いましょう。
晩秋になると、ベイトを探してもなかなか見つからないことがあります。
そこで、ベイトを探すよりもベイトの溜まりそうな場所を探すように心掛けましょう。
秋爆の10月を越え、11月前半の海は静かで落ち着いてきます。ベイトは全体的に減りますが、水中の変化には部分的にベイトが残っています。そのため、変化を読むことで晩秋シーバスを狙うチャンスはまだまだあります。ま[…]
デイゲームでの狙い方
4.jpg)
基本はボトム狙い
シーバスはもともと夜行性であるため、日中はボトム付近を回遊する傾向にあります。
とはいえ、ボトム付近で定位しているわけではりません。
ボトム付近には底棲性のベイトがたくさんいるので、日中でもシーバスは普通に反応してくれます。
そこで、晩秋のデイゲームではボトム付近のシーバスを狙うのが基本的なアプローチです。
中層を回遊するシーバスも拾う
日中は、一見すると静かな水面であっても、水温が高いとベイトを探して中層を回遊しているシーバスがいます。
このようなシーバスは捕食スイッチが入っていることがあるため、シーバスさえいれば一発で食ってくることさえあります。
そのため、中層を回遊するシーバスも取りこぼさずに拾っていきましょう。
水温の高い晩秋の狙い方
2.jpg)
1か所に固執せず場所を移動しながらテンポよく探す
秋が深まれば深まるほど、ベイトの魚影が薄くなっていくため、回遊性のシーバスに出会える確率は下がっていきます。
つまり、水中の変化の少ない場所で粘っていてもなかなかシーバスには出会えないということです。
そのため、1か所で粘るよりも「10~15分で割り切って移動する」というくらいの見切りの早さが必要です。
風の弱い日=チャンス日
風が弱いと表層の水が動きにくいため、ベイトが散らばりにくくなります。
また、水の撹拌が起こりにくく、水温も安定するため、結果としてベイトが1か所に溜まりやすくなります。
つまり、風が弱い日にはベイトが散りにくい自然条件が揃うときといえます。
そのため、風が弱い日には積極的に晩秋シーバスを狙ってみましょう。
冷え込み後のシャローエリアには要注意
急激な気温の低下が発生しても、海水温の低下は遅れてやってきます。
そのため、基本的には水温の急激な低下を心配する必要はありません。
ただ、シャローエリアは水量が少なく、気温の低下による影響を受けやすいエリアです。
急激な冷え込みによりシーバスのポジションが一気に冬寄りへ移動する可能性もあるので注意しましょう。
前日までの“秋の名残り”が急に消えてしまうこともあります。
水温の高い11月後半は秋の名残りを味方にする
3.jpg)
水温15℃前後で迎える11月後半は、本来の季節感より数週間ほど秋が続く珍しいシーズンです。
表層~中層に残るシーバスの気配を探すことで、例年以上に面白い晩秋の釣りが成立します。
ハイシーズンのルアーや狙い方がそのまま効いたり、ハイシーズン同様に複数本のランカーを一晩で釣り上げることもあります。
ベイトの群れは散発的になって狙いをやや絞りにくくはなりますが、その季節にしか味わえない“秋の名残り”を楽しみましょう。